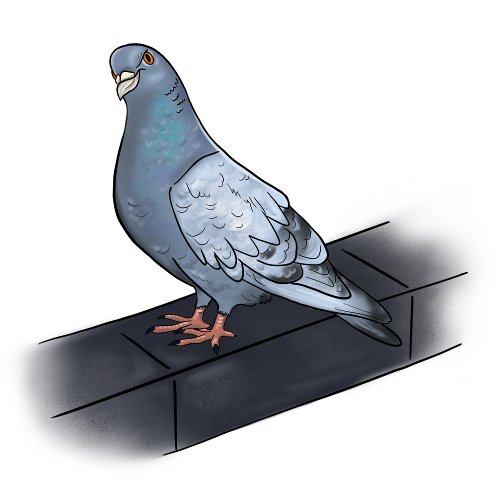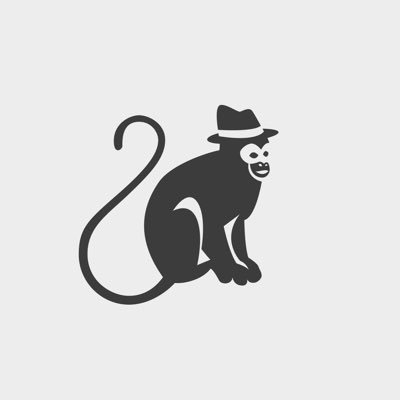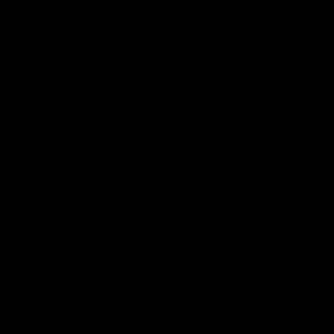松本太一@アナログゲーム療育
@gameryouiku
Followers
11,091
Following
1,849
Media
99
Statuses
6,957
東京学芸大学大学院卒業教育学修士。自閉症児療育「太田ステージ」開発者太田昌孝先生に師事。 市販のゲームを使ってルールの守り合いの成功体験を作るアナログゲーム療育を提唱中。弓道参段 放課後等デイコンサルはこちら→ @houkagodays
東京都 青梅市
Joined October 2010
Don't wanna be here?
Send us removal request.
Explore trending content on Musk Viewer
SnowMan
• 169313 Tweets
#WEARE大阪生配信やで
• 168951 Tweets
Malema
• 96710 Tweets
海ちゃん
• 69642 Tweets
ナイトメア
• 66095 Tweets
Zuma
• 39898 Tweets
見逃し配信
• 38547 Tweets
Azra Kohen
• 35245 Tweets
BINI SA ISLANG PANTROPIKO
• 29139 Tweets
Eastern Cape
• 24523 Tweets
Ley de Amnistía
• 21456 Tweets
ライドカメンズ
• 21012 Tweets
Ruanda
• 17295 Tweets
Gauteng
• 15912 Tweets
Limpopo
• 15431 Tweets
Zulu
• 15197 Tweets
トラジャ
• 13660 Tweets
上田くん
• 13158 Tweets
元太くん
• 12588 Tweets
大橋くん
• 11624 Tweets
ジュンブラ
• 11600 Tweets
重岡くん
• 10966 Tweets
シンデレラガール
• 10329 Tweets
リンライ
• 10250 Tweets
Last Seen Profiles
私は近頃「障害者枠就労」は発達障害のある人にとって必ずしも向いていないのではないかと考えるようになった。というのも障害者枠の仕事は、長期の就労継続が難しい人の多い現状を踏まえ他人でも代替可能な業務を設定する場合がほとんどだからだ。それゆえ、評価軸が仕事のスピードや精度、勤怠の安定
8
186
635