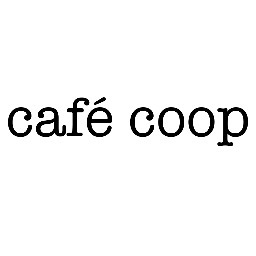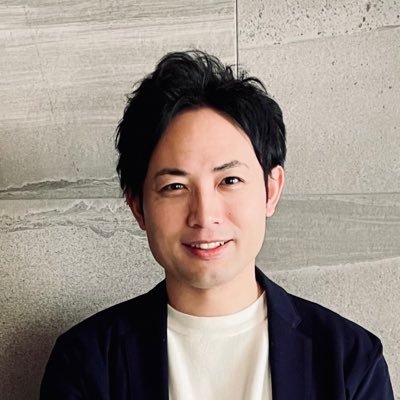
Koei Sasaki
@KoeiSasaki
Followers
3,978
Following
172
Media
494
Statuses
3,125
専門領域は発達障害/Voicyパーソナリティ公認心理師/臨床心理士/精神保健福祉士/よこはま発達グループ/TEACCHプログラム研究会東北支部代表/(株)クロス・カンパニー(障害×デザイン)アドバイザー/講演依頼等お仕事に関する相談はDMをご活用ください。
Joined November 2020
Don't wanna be here?
Send us removal request.
Explore trending content on Musk Viewer
No Riley
• 515187 Tweets
Chile
• 192676 Tweets
#Smackdown
• 131793 Tweets
Perú
• 118462 Tweets
Oilers
• 81265 Tweets
#NuNew1stConcert
• 67087 Tweets
Game 7
• 51298 Tweets
THE UNTOLD CINEMA PREMIERE
• 51267 Tweets
#holoJustice
• 50963 Tweets
Edmonton
• 48074 Tweets
Panthers
• 43768 Tweets
Alexis
• 40237 Tweets
Elizabeth
• 39445 Tweets
Gigi
• 31490 Tweets
Jacob Fatu
• 30398 Tweets
MIRANDO LOS 8 ESCALONES
• 25613 Tweets
EVANGELISTAS FURIOSOS
• 16927 Tweets
エンゼルス
• 14880 Tweets
Osorio
• 11057 Tweets
MINA IN MALAYSIA
• 10303 Tweets
Last Seen Profiles
自閉スペクトラムについて、今ではその言葉は認知されるようになってきたと思いますが、その分多くの情報があります。
僕としては、
@ChiyodaClinic
の解説がとてもわかりやすいと思いますし、誤解のない内容だと思っています。
iPECのHPは下記です↓
#発達障害
3
254
1K
エコラリアについて大事なこと。
・同じ独り言でも状況によってその意味は違うことを知っておく
・不安に耐えたり、切り替えのために用いられていることもある
・どのような場面で目立つのか/目立たないのか、それぞれの状況でどんな違いがあるのかを整理する
・その上で対処を考えてみる
今回はエコラリアについてテキストで解説してみました。
"エコラリアには、言葉をただ反復をしているようにコミュニケーションの意味を持たないものもあれば、中にはコミュニケーションの意味を持つものもあります"
エコラリアにもバリエーションがある
@KoeiSasaki
#note
3
31
129
6
313
1K
ASDの方々の支援現場では、「どう本人を説得するか」という視点ではなく、“説得ではなく納得が大事であること”、“理解と納得は別であること”という視点が大切で、自分もいつもそれを念頭に入れておきたいと思います。#自閉症スペクトラム
#TEACCH
#発達障害
1
61
252
我々よこはま発達グループで、5月から「よこはま発達サポートルーム」という児童発達支援事業等をスタートします。チラシとHPも完成しました。多くの方々とご一緒できるようにと思いますし、よい療育モデルを作っていけるようスタッフ一丸となって取り組んでいきたいです。
@TokioUchiyama
1
30
194
合理的配慮は「なんでも対応します」というものではありません。
2016年4月1日に施行された障害者差別解消法で定められた合理的配慮。行政機関等は義務で、それ以外は努力義務でした。
2024年4月1日からは義務化されましたが、どの程度社会の人に認知されているかというと、まだまだかもしれません。
#Voicy
#合理的配慮
#発達障害
0
9
26
2
56
194
所属しているよこはま発達グループにて、内山先生(
@TokioUchiyama
)と共に、発達検査の意義と誤解についてディスカッションしました。
診断に検査は必須ではありません。でも、支援を考えた時には役にたつものだと思います。
宜しければご視聴ください。
0
24
138
放送した内容について記事でもまとめています。
記事の要約は下記です。
・非常時には混乱することを前提に、情報整理をする
・予測がつかないということを含め見通しを伝える
・できるだけストレスの少ない過ごし方を、ご本人・ご家族にも提案する
今現地で必要な情報ではないと思います。
現地ではライフラインに関することが最優先です。
それでも、少しでも、どこかの、誰かのお役に立つ可能性があるのであればと思って、昨年3月11日にTEACCH研東北支部の皆さんに配信した内容をもとに話をしました。
#Voicy
0
34
99
0
60
132
障害福祉の現場では、「支援つき意思決定支援」という言葉があります。これは、「自分で決めてください」とだけするのではなくて、自己決定することをサポートした上で、決めてもらう、つまり「決めやすくするように支援する」という意味です。
「意思決定支援」についてご質問を頂いたのでVoicyで話をしてみました。実際にはとても難しいし、考え続けるテーマだなと思います。
ただ、「決定だけを求める」のではなく、そうした判断をどうサポートするかが重要なことなんじゃないかと、僕は思っています。
#Voicy
0
11
33
4
42
131
今回はエコラリアについてテキストで解説してみました。
"エコラリアには、言葉をただ反復をしているようにコミュニケーションの意味を持たないものもあれば、中にはコミュニケーションの意味を持つものもあります"
エコラリアにもバリエーションがある
@KoeiSasaki
#note
3
31
129
TEACCHはアメリカのノースカロライナ大学を拠点に実施されているプログラムで、それらの頭文字をとってTEACCHとなっています。ちなみに、TEACCHの意味は下記図をご参照ください。
自閉症支援の始まった頃は、自閉症の原因は親御さんであり、親御さんが治療や批難の対象でした。
TEACCHの考え方がぼくは好きなのですが、色々と誤解をされているんじゃないかと思おうこともしばしばあります。
今回はTEACCHが大切にしている哲学の一つについてお話をしました。少しずつ、ぼくが思うTEACCHの誤解についても取り上げていきたいと思っています。
#Voicy
0
12
32
0
31
124
❶障害について、国際生活機能分類(ICF)では、健康は個人だけの問題ではなく、環境の影響も大きいとしています。
❷そのため、障害を持つ方々が直面する問題は、個人の体の問題だけではなく、環境や社会の仕組みも大きく影響します。
0
49
121
感覚の敏感さは、慣れることはあまりなく、苦手な感覚にさらされる時間が増えることでむしろ不安が強くなり、より敏感になりやすいです。
慣れではなく、生活上の安心感が増えることで、敏感さが緩まることはよく経験します。
1
36
122
ぼくらは、検査の限界を知っておく必要があります。
診断のつく方でも凸凹のない方はおられますし、プロフィールだけで何かを断定することはできません。
検査の勉強ではなくて、支援のための検査ができるような勉強をしていく必要があり、そうした勉強のために最適な一冊ではないでしょうか。
1
19
119
【4月2日は世界自閉症啓発デーです】
本日は世界中で自閉症の方々を知って頂くための活動がなされています。
我々も啓発に関する動画を約1週間に渡って配信したいと思います。理念の一つである、Autism Friendlyな地域をめざして。
#世界自閉症啓発デー
@TokioUchiyama
1
35
117
以前、内山先生(
@TokioUchiyama
)から教えて頂いたことです。
いつの場面、状況でも大切な考え方だと思います。
#障害者を消さない
0
27
111
【正しい知識と啓発のために】
よこはま発達グループは、内山登紀夫先生(
@TokioUchiyama
)を代表に、医療部門と療育部門を設立し、これまで発達障害に関する研究や支援に携わってきています。
そうした中、4月1日に放送されたABEMA
0
41
100
発達障害領域で「カモフラージュ」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?海外だと「マスキング」と呼ばれたりします。
これは、自分の特性を隠して、特性がないかのように振る舞っていることがあり、こうした補正をしながら生活していることを指しています。
今日のテーマは「カモフラージュ」です。マスキングと呼ばれたりすることもあります。
誰しも自分の行動は補正することがありますが、そのことで疲れすぎてしまう方々がいます。
できている、スキルが増える=OKというわけではないこともあります。
#Voicy
0
12
27
1
35
106
今現地で必要な情報ではないと思います。
現地ではライフラインに関することが最優先です。
それでも、少しでも、どこかの、誰かのお役に立つ可能性があるのであればと思って、昨年3月11日にTEACCH研東北支部の皆さんに配信した内容をもとに話をしました。
#Voicy
0
34
99
時間や場所を共有するのはインクルーシブ教育ではありません。時間や場所を共有しながらも、それぞれが参加し、学びやすいスタイルで学べることがインクルーシブ教育ではないでしょうか。
神奈川県のニュースをもとに、インクルージョンやダイバーシティについて、僕の考えを改めて。
いずれも賛成ですが、必要かつ具体的な調整がなければ、誤解や偏見を助長することにも繋がりかねません。
「一緒にすればいい」という、単純なものではないのです。
#Voicy
0
14
28
0
25
97
「好きなことや得意なことがない」
「その質問が一番困る」
そうしたことを聞くことがあります。
支援者の方からも、「得意を活かすとよく言われますが、得意なことや好きそうなことがない場合はどうしたらいいのでしょうか?」とご相談をお受けすることがあります。
1
20
92
内山先生(
@TokioUchiyama
)が中心になり、この領域で著名な先生方が「感覚の偏り」について、さまざまな切り口で書かれています。
僕自身は「感覚をめぐる困りごとを抱えるASDの子どもを支える視点」というテーマで書かせていただきました。
@afcp_01
先生に総論を書いていただいており、
4
30
89
世界中で啓発のための活動がなされています。
我々よこはま発達グループとしても、毎年啓発を兼ねた動画を配信しています。
内山代表(
@TokioUchiyama
)、宇野副院長、佐々木の3名で、今、改めて大切にしたいことについてディスカッションしています。
よければぜひ!
0
35
81
自閉症スペクトラム特性の一つに「社会的イマジネーション」というものがあります。聞き馴染みのない言葉かもしれませんが、「目の前にないことを推測したり、柔軟に、臨機応変に応じていく力」のことを指しています。
今日のテーマは「こだわり」です。
・こだわり自体は問題じゃない
・生活上の不都合がなければ、「それもありかも」と認めてもよいのでは?
・生活で不都合が生じている場合には対応を考える
・ただし、本質的な問題は「こだわること」ではない
みたいな内容です!
#Voicy
0
7
28
0
18
76
世間的にはクリスマスシーズンに入っており、多くの方々にとっては楽しみな時期かもしれません。でも、一部の自閉症スペクトラムの方々にとっては楽しみではない、むしろ難しい時期と感じることもあります(ワクワクしにくい)。
本当はこっちのテーマを話そうと思っていたのですが…
でも、今日くらいしか話すチャンスもないので、追加で収録しました(というか、もっと早くに話せばよかったのですが💦)。
皆さんにとって、よいXmasになりますように🎄
#Voicy
0
5
16
3
24
74
ヘラルボニー(
@heralbony
)さんが
#障害者を消さない という取り組みをしてくださっていることを知りました。
自分の発信した内容が少しでもお役に立てばと嬉しく思います。
こうした旗を立ててくださったことに感謝しています。
0
30
75
知能検査はよく実施される検査の一つです。でも、それを支援に活かせるかどうかは、「誰が検査をとるのか」によって大きく違います。
支援に活かすためにはどのような視点が必要なのか、内山先生(
@TokioUchiyama
)、北沢先生、佐々木の3名で実践型の研修会を行います。
1
12
74