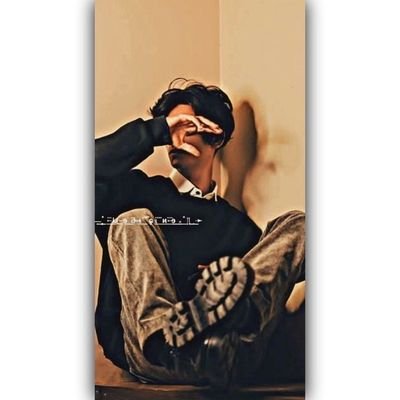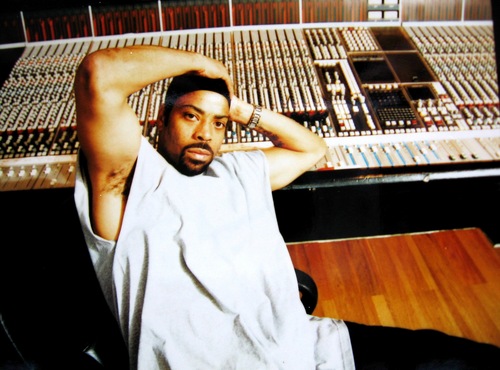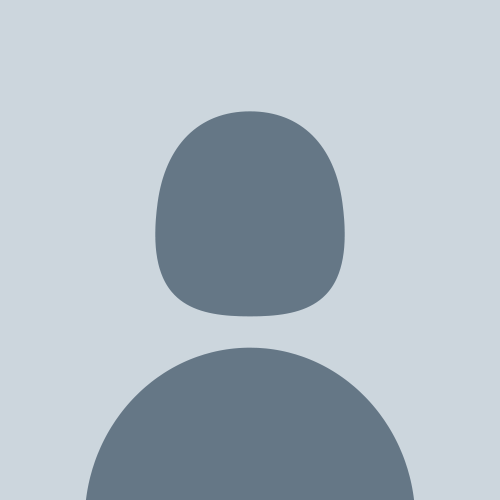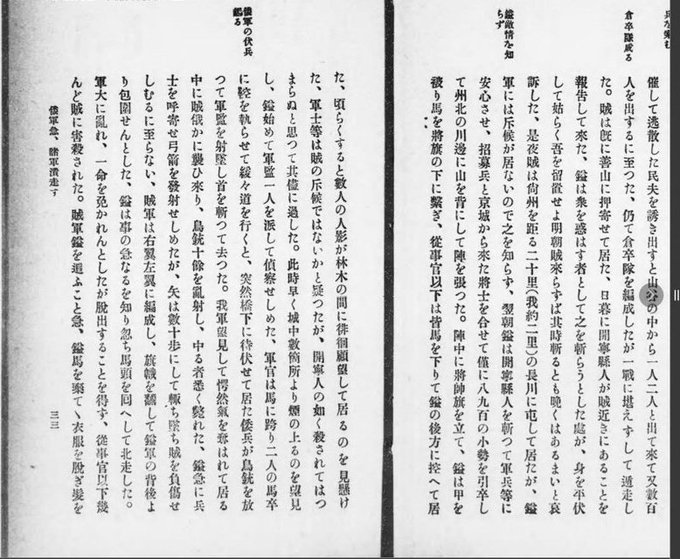あの夏
@DBo2750puu0hfu3
Followers
1,566
Following
968
Media
1,989
Statuses
6,504
日本酒愛好者🍶 大学時代は日・明・朝三国の武芸が修練されていた朝鮮の軍営「訓錬都監」について研究。 無言フォローさせていただく場合がございますが、もし不愉快でしたらどうかブロックしてください…… こちらは無言フォロー大歓迎です!
新潟
Joined October 2016
Don't wanna be here?
Send us removal request.
Explore trending content on Musk Viewer
HAPPY 3RD BINIVERSARY
• 152327 Tweets
Ciotti
• 92053 Tweets
#TimnasDay
• 45251 Tweets
うたコン
• 31219 Tweets
刀剣男士
• 27335 Tweets
オリックス
• 27276 Tweets
ライエモ
• 20375 Tweets
VIVA CARNIVAL
• 13222 Tweets
ジャクソン
• 13173 Tweets
Thom Haye
• 11525 Tweets
Last Seen Profiles
プレートアーマーの価格について
(写真がうまく撮れてないが😅)
この記述がどこまで正確かわからないが、15世紀中期頃のミラノ式プレートアーマーは「8ポンド6シリング8ペンス」で、これは現在の貨幣価値に換算すると約170万円程
従者用なら6ポンド(約120万円)と、思っていたよりは安い印象
1
92
179