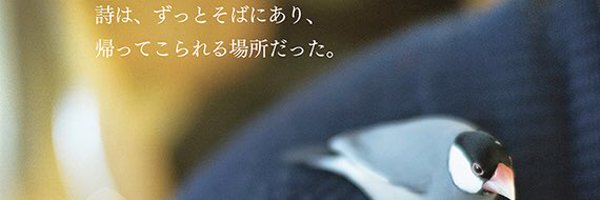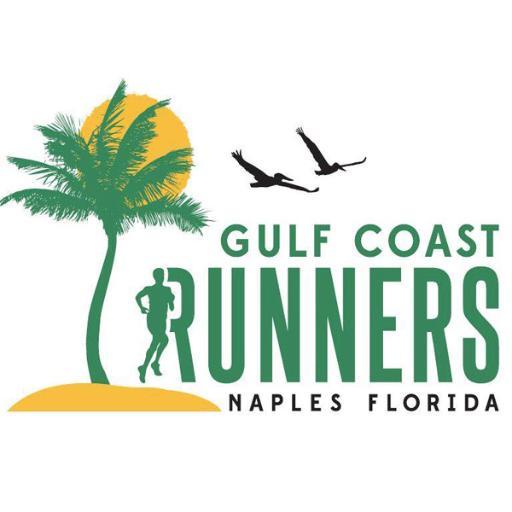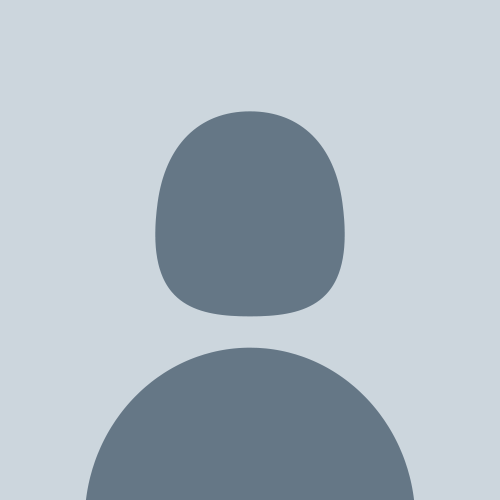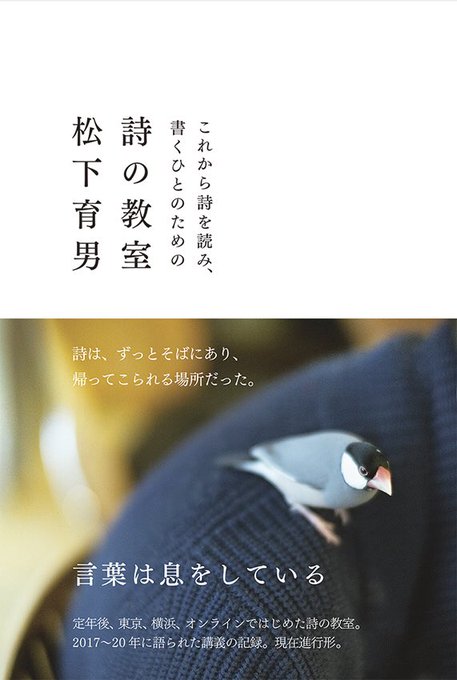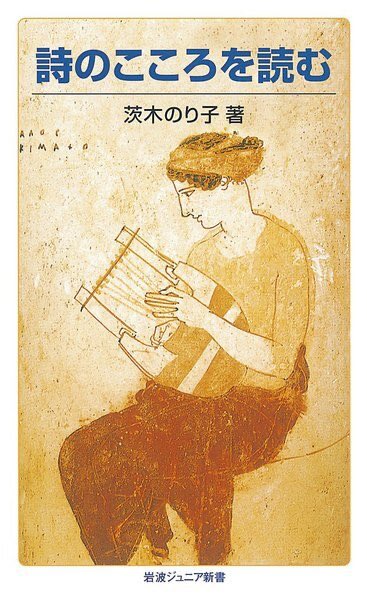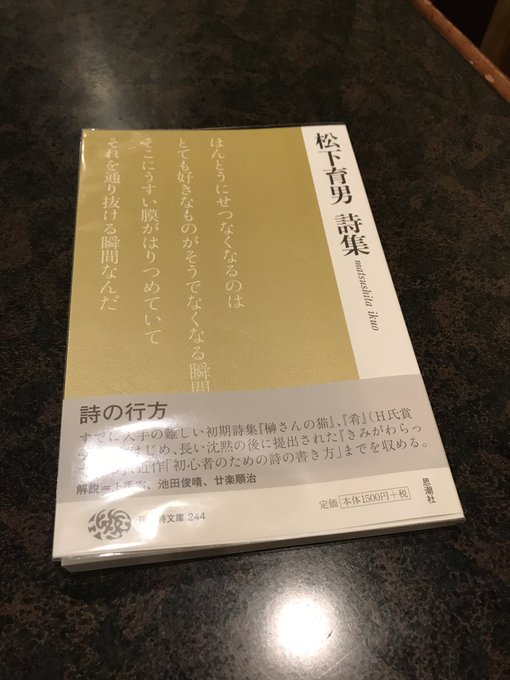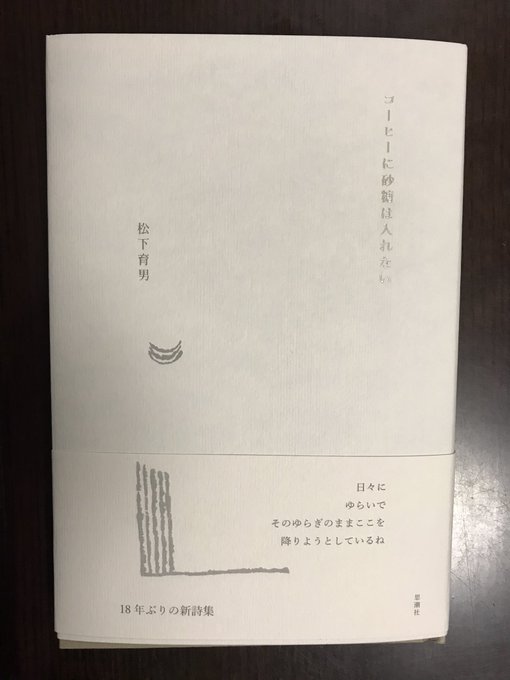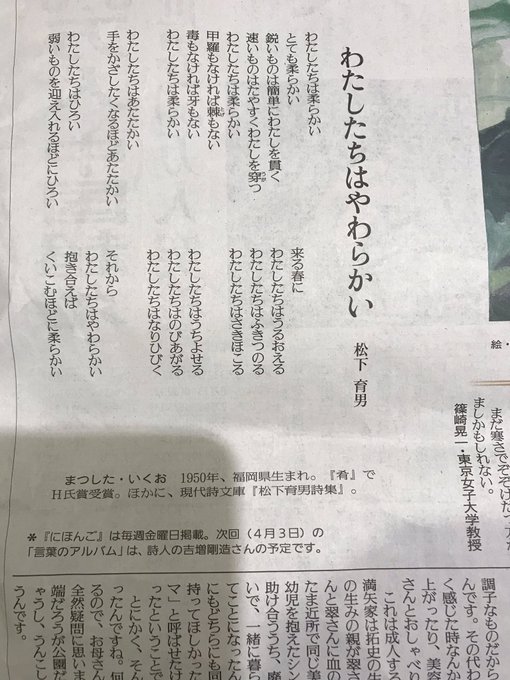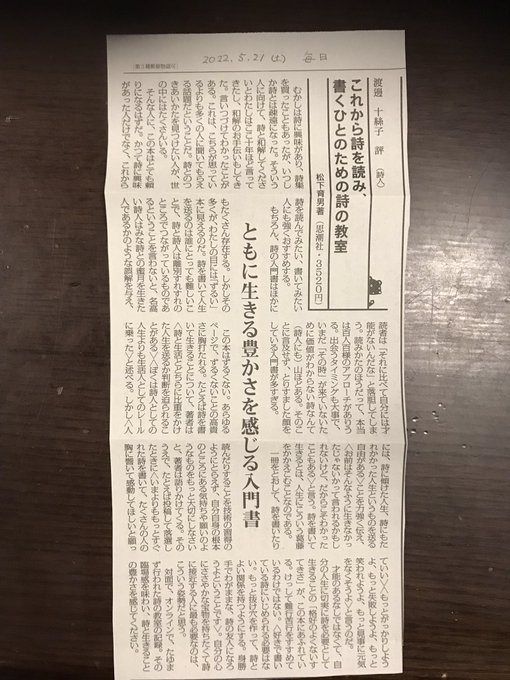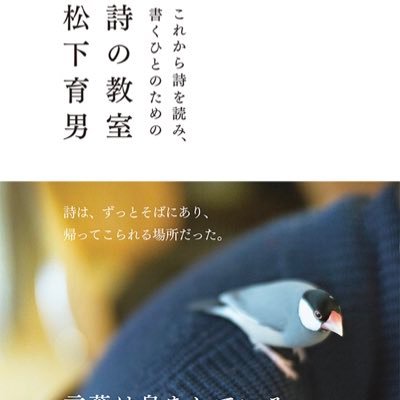
松下育男
@fampine
Followers
4,194
Following
113
Media
1,440
Statuses
7,813
詩とともに生きる。詩集『肴』(H氏賞)、他。詩の教室をやっています。現代詩文庫『松下育男詩集』、詩集『コーヒーに砂糖は入れない』講演録『これから詩を読み、書くひとのための詩の教室』発売中。
Joined August 2010
Don't wanna be here?
Send us removal request.
Explore trending content on Musk Viewer
Modi
• 1008290 Tweets
Farage
• 420452 Tweets
Nigel
• 316212 Tweets
Begoña
• 217745 Tweets
Garland
• 149229 Tweets
Sunak
• 124624 Tweets
Grabois
• 70957 Tweets
Keir
• 70515 Tweets
OBMEP
• 68072 Tweets
Halsey
• 55818 Tweets
Rihanna
• 49486 Tweets
Checo
• 46898 Tweets
Chainsaw Man
• 38644 Tweets
#ITVDebate
• 36344 Tweets
Red Bull
• 35767 Tweets
Fujimoto
• 33662 Tweets
Denji
• 29751 Tweets
Bancolombia
• 27361 Tweets
Isabella
• 25666 Tweets
Yoru
• 22680 Tweets
Fenty Hair
• 19464 Tweets
Sainz
• 15918 Tweets
Beele
• 14711 Tweets
#BorsadaVergiyeHayır
• 13992 Tweets
Alcaraz
• 13462 Tweets
Brukseli
• 11401 Tweets
#KohLanta
• 10789 Tweets
Bruno Fernandes
• 10353 Tweets
TRES DE FEBRERO
• 10163 Tweets
Last Seen Profiles