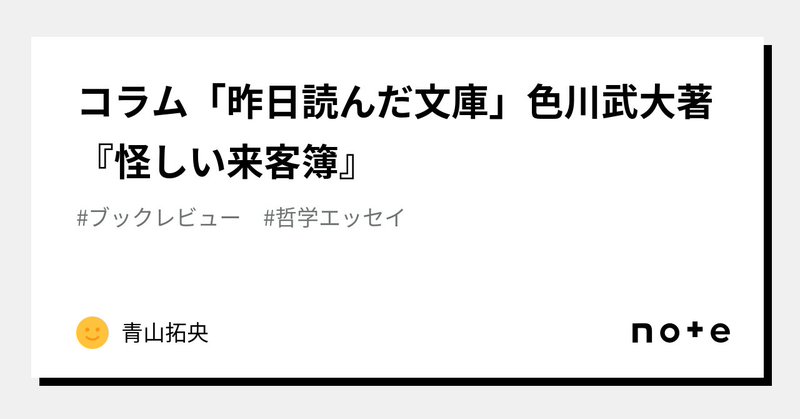青山拓央 / Takuo Aoyama
@aoymtko
Followers
6K
Following
5K
Media
23
Statuses
2K
京都大学の哲学の教授 / Professor of Philosophy, Kyoto University. 著書に『時間と自由意志』『幸福はなぜ哲学の問題になるのか』『分析哲学講義』など。執筆依頼等は下記URLにて。
Joined April 2011
RT @yamaguchi__sho: 哲学史の本を出します(次の火曜日発売)。. 論じられるのは1970年代から21世紀のテン年代あたりの日本の哲学。すなわち現代日本哲学。. 哲学を専門としないひとにも、するひとにも、複数のレベルで役立つよう工夫された作品です。. 《哲学史と….
0
99
0
RT @hitoshinagai1: 「親ガチャ」は基点を自分である特定の人間に置ける(そいつから見ての「親」にかんするガチャと)が、「自分ガチャ」はそれができない(その特定の人間であることにかんするガチャなので)。後者にかんしては、独在性を前提にしないとその意味そのものが理解….
0
38
0
RT @asonosakan: 新しい論文「物理学における決定不能性と強い創発」のプレプリントをresearchmapに公開しました.昨年,時間・偶然研究会の「強い創発をつくる」WSで発表した内容を論文化したものです.よろしくお願いします...
0
21
0
こちらのノートも併せてどうぞ。哲学者 vs 科学者 という粗雑な二分化が、誤読を招く実例が書かれています。.
note.com
《哲学者にはあらかじめ守りたいものがあり、それを守ることを目的として理屈を並べている》という思い込みは、哲学の文章を誤読させやすい。実際には書かれていないことを行間から変に読み取ってしまい、それへの攻撃欲が増すことで、文章を精確に読めなくなってしまう。 例をひとつ挙げておこう。リベットの実験によって自由意志は否定されたという話は、メディアでよく紹介される。だが、詳細を見ていくと、この話には多...
0
4
23
RT @mieko_kawakami: 3年前の8月に文庫になった『夏物語』、ありがたいことにずっと版を重ねていて、この度も、こんなに熱い言葉を寄せていただき新帯を巻いての大重版となりました。本当にありがとうございます。40以上の言語に翻訳されて、世界中の読者から感想をちょうだ….
0
113
0
RT @adamtakahashi: 「他人の毒素を体内に射込み、自分の毒素と中和させることで、ようやく生きていけるような弱さである。」. コラム「昨日読んだ文庫」色川武大著『怪しい来客簿』|青山拓央 .
note.com
(毎日新聞 2016. 3. 6. 朝刊に掲載) 色川武大の『怪しい来客簿』(文春文庫)をほぼ二十年ぶりに再読する。やはり、べらぼうに文章がうまく、べらぼうに心の一点が弱い。その弱さは多くのひとに共感を得られる種類のものではないが、それはちょうど、他人の毒素を体内に射込み、自分の毒素と中和させることで、ようやく生きていけるような弱さである。 同書の『たすけておくれ』という掌編中の「私」は、胆...
0
4
0
そう言って頂けて光栄です!.文学論と呼べるようなものを書いたことはないのですが、個別の文学作品について短い文章を書いたことはあり、たとえば、色川武大について毎日新聞にこんな短文を載せました。.
note.com
(毎日新聞 2016. 3. 6. 朝刊に掲載) 色川武大の『怪しい来客簿』(文春文庫)をほぼ二十年ぶりに再読する。やはり、べらぼうに文章がうまく、べらぼうに心の一点が弱い。その弱さは多くのひとに共感を得られる種類のものではないが、それはちょうど、他人の毒素を体内に射込み、自分の毒素と中和させることで、ようやく生きていけるような弱さである。 同書の『たすけておくれ』という掌編中の「私」は、胆...
1
4
12