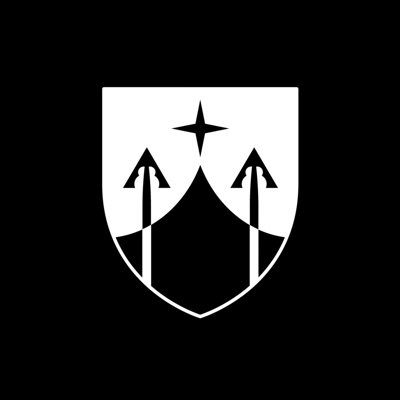藤井動物病院FVMC(WBC動物病院グループ)
@FujiiACC
Followers
103K
Following
65
Media
58
Statuses
10K
横浜市の藤井動物病院の院長のツイッターです。X上での返信はしておりません。個別の犬猫の問題はそれぞれ違いますので主治医にご相談下さい。よろしくお願いいたします。このツイートは日々の動物との生活の参考にしていただけたら幸いです。拙著「家ねこ大全285」、「いぬ大全304」KADOKAWA よろしくお願いします。
横浜市港北区菊名1-14-11
Joined May 2011
香箱座りは“安心の証”です。前足をしまって体を丸める姿勢は、体温を逃さず、周囲への信頼を示すサイン。ただし前足がしまえない、内向きに曲げたままの子は、手首や肘の関節炎などの痛みを抱えていることもあります。静かで温かな定位置を整える、季節で寝床素材を替える、座り方の左右差を観察。“油
0
39
104
散歩中に草を食べるのは、犬にとって珍しい行動ではありません。胃腸の調整や食物繊維の補給、匂いや食感を楽しむ探索行動、さらには口寂しさやストレス発散など、いくつかの理由が関係すると考えられます。少量で体調に変化がなければ生理的な範囲ですが、除草剤のある場所は避けてください。また嘔吐
0
26
63
Science is about a total commitment to truth. We are probably better off knowing the truth about all contentious matters, although there are no guarantees about the outcome. Dr Bret Weinstein @BretWeinstein sets out the terms of engagement for scientific enquiry done properly.
1
0
13
仕事帰りに玄関で待つ猫、それは“時計”ではなく記憶で動く行動です。猫は足音や匂い、光の変化を組み合わせて「そろそろ帰ってくる」と学習しています。人の生活リズムを読み取るその賢さは、日々の安心の証です。帰宅時に声をかけてあげる、やさしく触れる、生活リズムを保ってあげる。猫は時間ではな
16
990
5K
靴下や服をくわえて運ぶ犬は、“いたずら”ではなく安心を求めています。飼い主の匂いがついたものは、群れの香りのように心を落ち着かせる存在です。留守中や夜間に見られることもあります。取り上げずに見守る、安全なぬいぐるみを交換で渡す、帰宅時にやさしく褒めることが大切です。こういった行動は
2
193
972
窓の外に反応して吠えるのは、“うるさい”のではなく、外の異変を知らせる本能的な警戒行動です。犬は人の約4倍の高い周波数を聞き分け、遠くの足音や車の音にも反応します。私たちには静かでも、犬には情報があふれている世界です。吠えすぎるときは、遮音カーテンを使う、刺激源を減らす、落ち着いた
0
233
1K
猫が何もない空間をじっと見つめるのは、“幽霊”ではなく、私たちに聞こえない高周波音や光のちらつきを感じ取っているからです。猫の感覚は人よりずっと鋭く、見えない刺激を察知して反応しています。驚かせずに見守ってあげて、照明や家電の音を点検してください、異常が続くときは受診を。猫が見てい
3
492
2K
猫が棚や冷蔵庫の上に登るのは、“高いほど安心”という本能の表れです。外敵を避け、周囲を見渡すことで安全を確かめています。立体的な空間を持つ環境は、ストレスや緊張の軽減���も役立ちます。キャットタワーを設置し、安全に登れる動線を確保する、無理に降ろさない。高い場所でくつろぐ姿は、安心で
2
316
1K
名前を呼ぶと首をかしげる犬、その可愛い動きには科学的理由があります。耳介(じかい)を傾けて音源を正確に捉え、同時に声のトーンや表情を読み取っているのです。この仕草は、相手への理解や共感のサインとも考えられます。名前を呼んで目を合わせる、反応を褒める、写真に残して楽しむ。小さな首の
0
246
1K
気持ちよさそうに撫でていたのに突然“ガブッ”。これは愛撫誘発性攻撃と呼ばれる防衛反応です。気持ちよさのピークを越えると「もう十分」というサインです。尻尾の動きを観察して、耳が伏せたらやめる、優しく声をかけて距離を保つ。猫のボーダーを理解することが信頼関係の鍵です。#藤井動物病院
4
568
3K
どこへ行っても犬が後ろをついてくる。これは“甘え”ではなく、群れで生きる本能からくる行動です。リーダーの動きを確認することで安心し、信頼が深いほどその同調行動は強くなります。一緒に動く時間を増やす、落ち着いた声で話しかける、留守番の前後は穏やかに接する。ついてくる足音は、信頼と愛情
3
306
2K
寝ている犬の足がピクピク動くのは、レム睡眠中に夢を見ている証拠です。走る、遊ぶ、飼い主と過ごす。そんな夢を見ている可能性があります。脳の活動は人の夢ととても近いことがわかっています。起こさず静かに見守る、寝床を快適に整える、眠る前は穏やかな時間をつくる。夢の中でも犬は、大切な一日
3
290
2K
トイレ後に砂をかけない猫は、実は“無言のサイン”かもしれません。排泄後に立ち去る行動は、ボス的な自己主張のほか、砂の感触や臭い・音など環境への不快感が原因のこともあります。多頭飼いでは、他の猫への優位アピールになる場合もあります。もし変化が有ったら、砂の種類を変える、静かな場所に置
1
324
2K
寝る前や朝方に鳴くのは、猫が“薄明性動物”だからです。明け方や夕暮れに活発化し、飼い主を“狩り仲間”として誘っている可能性もあります。おうちでは、就寝前に軽く遊ぶ、朝は静かに対応、決まった時間に食事をあたえてください。猫の体内リズムを知ることで、生活の調和が保てます。#藤井動物病院
3
372
2K
眠る前にくるくる回るのは、草むらで寝床を整えていた祖先の習性と言われています。体温調節と安全確認のための儀式的動作です。おうちでは、柔らかい寝床を用意して、安心できる静かな場所を選んでください。そして寝る前の声かけを。眠りの準備にも、進化の名残があります。#藤井動物病院
0
257
1K
パソコンの上や書類に座る猫。これは「飼い主の注意を引く」ための社会的学習行動です。反応してもらうたびに“構ってもらえる”と覚えていきます。家庭でできることは、代わりに猫用スペースを設ける、静かに抱っこして離す、遊び時間を定時にする。猫も人と同じで、日課と交流が心の安定をつくります。
4
401
2K
排泄後に地面を蹴るのは「隠す」ためではなく、“ここにいたぞ”という足裏マーキングと言われています。飛び散る砂も誇示的シグナルです。安全な場所で排泄させてください、近くに人がいる時は距離を取り、トイレ後の癖を観察してください。犬にとって排泄は縄張りの明かしでもあります。#藤井動物病院
1
180
1K
犬が顔を舐めるのは、子犬が母犬の口元を舐めて食べ物をねだったときの名残りです。現在では愛情や服従のサインとして表れます。穏やかに受け止めてください、過剰なら静かに離れることが大切、清潔を保つ。舐める行為は“信頼のあいさつ”のようなものです。#藤井動物病院 #横浜市動物病院
1
239
1K
なぜ猫は狭い箱や袋に入りたがるのでしょう。捕食者から身を守る“安全地帯”を求める本能的行動です。体温保持にも役立ち、研究ではストレス軽減効果も示されています。家庭でできることは、箱やトンネルを用意、急に取り上げない、汚れたら静かに交換してください。猫が落ち着く“自分の隠れ家”を持つと
0
376
2K
猫が飼い主の顔や手を舐めるのは、社会的グルーミング(アログルーミング)の一種です。親猫が子を舐めて絆を確かめるように、信頼と愛情のサインでもあります。時に塩分や匂いへの好奇心も混ざります。家庭でできることは、無理に避けず受け入れる、過剰なら静かに離れる、清潔を保つ。舐める行為は“
4
496
3K
帰宅時に大はしゃぎするのは、ただの喜びではありません。“群れが再びそろった”という安心反応で、脳内のドーパミンとオキシトシンが上昇します。こういったときは、落ち着いた声で挨拶する、興奮が収まったら撫でる、日課の再会ルールをつくる。感情の波も理由があります。#藤井動物病院
4
556
3K